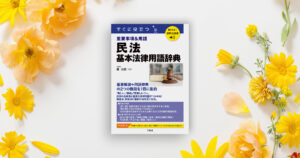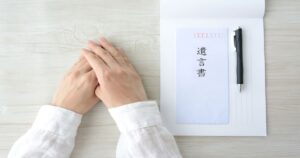相続税額の基礎控除額

相続税額の基礎控除額は、結構変わりますが、現在は、以下の計算式で求めます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
年々、基礎控除額が減少しています。そのため、年々、納税義務が発生する相続案件も増え、現在は、相続案件の10%以上は相続税申告対象になると言われています。
法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が増えますが、だからといって、養子縁組して子どもの数を増やしても、相続税法では、実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人に含めることができません。ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合、代襲相続で相続人になった養子は実子と見なされ、人数制限は受けません。
また、孫が養子になって祖父から相続を受ける場合、相続税法上では相続税の納税額を2割加算する制度が適用されます。もっとも、孫養子であっても子の代わりに代襲相続する場合は、2割加算の対象になりません。
それでは、相続放棄したらどうか。例えば、相続人が子どもは1人、しかし、その子の子、被相続人からすれば孫は5人いる、それなら子どもが相続放棄すれば、孫5人が相続人になるから、非課税枠が5倍になるかというと、そんな都合の良い話を国税は認めるわけがありません。相続時点で相続人が1人なら、放棄して法定相続人が5人になっても、1人として計算します。
もっとも、「相続放棄しても相続人の数は変えない」という原則は、納税義務者に有利な方向でも作用します。例えば、相続人は母を含めて5人だけど、子ども全員、母に相続させようとして相続放棄した場合、相続人は1人ですが、相続税法上は、5人で計算します。
死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」で求めます。このとき、法定相続人の中に相続放棄した人がいる場合でも、非課税枠の計算上は除外されません。しかし、そのみなし遺産を相続放棄した人が受け取っても、非課税枠は使えません。例えば、母親が子どもたちに相続させようと相続放棄する一方で、死亡保険金を受領しても、しっかりと課税されます。
非課税枠は、実際に相続した人が受け取った金額の割合で分け合いますから、子どもたちも死亡保険金を受領した場合などは、子どもたちがその枠を利用できます。