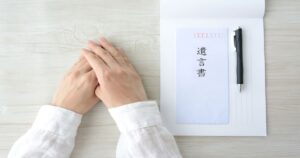要介護認定を受けていない場合の療養看護型特別寄与

現在、療養看護型特別寄与の認定は、要介護認定記録に基づいて行われている。この方式は、迅速かつ客観的に認定を行うことができるため、現在は、全国の裁判所で利用されるに至っている。言い換えれば、要介護認定を受けていない場合は、療養看護型特別寄与の認定を受けることは難しくなる。遺産分割調停・審判でも、要介護認定を受ければ受けられたが、被相続人がいやがったので受けていなかった、本来は要介護〇レベルだという主張は、介護した相続人らから日常的に出されるが、この主張が取り上げられることは、ほとんどない。これとは逆に、要介護〇というけど、本当は、もっと低かった、介護していた相続人が自治体をだましていたんだという主張も頻繁に出される。これも取り上げられることはない。療養看護型特別寄与が主張されるとき、介護していた相続人と介護していなかった相続人との間で、毎回、同じ非難合戦となる。どの事件でも、相続人の主張は、ほとんど同じだ。裁判所としては、どちらが本当かわからないから、介護認定記録で判断するしかない。
現実には、要介護認定を受けるべき事案なのに要介護認定を受けていないというケースはそれなりにあるが、その場合でも、療養看護型特別寄与が認定されることはほとんどない。
ところが、東京高決R5・11・28(家法57・70~)は、寄与分の申立てを却下した宇都宮家審R5・3・3事件につき、被相続人の病状等に照らし、被相続人が病院に入院するまでの3か月間の在宅介護について療養看護型特別寄与を認めている。この決定の決め手となったのは、おそらく「下の世話」だろう。療養看護型特別寄与では、寄与が特別か否かの認定では、排せつ行為が一人でできるかどうかが重要なポイントになっている。抗告人は、入院3か月前は、歩行器を使ってもトイレに行けなくなり、ベッド横のポータブルトイレを使用するようになったことを主張し、その立証として、写真やポータブルトイレ等の領収書(購入事実と購入時期の立証)を提出し、その他の医療記録で、要支援1からの介護の変遷を証明しようとしている。普通、排せつ行為が自力でできなくなると、たいていは施設に入れるか、要介護認定を受けてサービスを受けるものだが、本件では、看護師だったため、自力で対応できたという点も考慮されたものと思われる。
療養看護型特別寄与が認められるかどうかは、自力で生活できていたかどうかであるが、特に排せつ行為が自力でできないため介護したということは、明らかに扶養義務の範囲を超えている。この点が立証できれば、要介護認定を受けていなくとも、特別寄与と評価される場合もあるだろう。