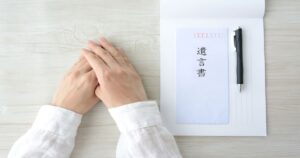遺留分侵害額請求に伴い取得した土地に小規模宅地の特例等は使えるか

【問題】
被相続人(令和元年8月1日相続開始)の相続人は、長男Aと長女Bの2名である。Aは、甲の遺言で宅地①(特定居住用宅地等)及び宅地②(特定事業用宅地等)を特定財産承継遺言で取得し、相続税の申告に当たってこれらの宅地について小規模宅地等の特例を適用して期限内に申告した。
しかし、Bから、遺留分侵害額の請求がなされ、遺留分侵害額請求債務の支払いにかえて、宅地②をBに支払うことで和解が成立した。
Bは、修正申告の際、宅地②について小規模宅地等の特例の適用を受けることができるか?
Aは、小規模宅地の特例を取り消されるか?
【回答】
結論からいうと、Bは、小規模宅地の特例は使えず、Aは、取り消されることはない。
遺留分侵害額請求では、意思表示により、請求権者には遺留分侵害額請求債権という「債権」を発生させ、被請求者には「債務」を発生させる。BがAに遺留分侵害額請求の意思表示をした場合、BがAに取得するのは債権であり、宅地②を譲渡したのは代物弁済である。Bは、相続や遺贈により取得したものではなく、相続後に代物弁済により取得したものである。したがって、小規模宅地特例の適用はない。
一方、Aは、相続税申告期限まで宅地②を所有していたから、申告期限後に譲渡したとしても、小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなるということはない。(国税庁質疑応答事例)
森法律事務所にご相談ください。(TEL:03-3553-5916)
夫婦親子問題 https://www.mori-law-office.com/katei/
遺産相続問題 https://www.mori-law-souzoku.com/