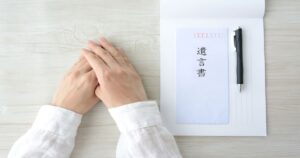賃貸不動産と小規模宅地の特例

相続地が租税特別措置法第69条の4に言う①「特定居住用宅地等」②「特定事業用宅地等」③「特定同族会社事業用宅地等」④「貸付事業用宅地等」のいずれかの場合、①~③に該当すれば、その「宅地」の「課税価格」が「評価額」の2割に、④に該当すれば「課税価格」が「評価額」の半額になる。
但し、限度面積要件があり、①は330平方メートル②③は400平方メートル④は200平方メートルであり、ここをオーバーした場合は、オーバーした部分は、通常の評価をされる。
面積には制限があっても、数には制限がないので、複数の「特定事業用宅地等」を所有している場合は、その面積の合計が400平方メートルに達するまで、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができる。
②の「特定事業用宅地等」と ③ の「特定同族会社事業用宅地等」は、400+400=800平方メートル まで適用を受けられるのではなく、「特定事業用等宅地等」として1つにまとめて考える為、両方の地積の合計が400平方メートルに至るまでしか、適用は受けられない。
金額については一切の制限が存在しません。
小規模宅地の特例は、本法である相続税法ではなく、政策的な意味から設けられる時限立法である租税特別措置法の第69条の4に規定されているから、本来は、時限立法なのだが、適用期間を制限していないので、事実上、相続税法等本法レベルで扱われている。
立法趣旨は、遺族の生活の維持である。相続税の税額負担が大きすぎるが故に、遺族が住み続けてきた家の敷地や事業に使用している土地を手放すことがないようにとの配慮である。
遺産分割にあたっては、そこに住む人が取得するような遺産分割をすれば、この特例が使えて、相続税全体が大幅に安くなる。
また、この制度は、貸地にも利用できる。被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業等の「貸付事業」。)の用に供されていた「宅地等」も減額対象である。
被相続人がアパートを所有していたら適用になるのは当然だが、被相続人が有していた土地に長男が使用貸借としてアパートを建てる一方、長男が被相続人と生計が一緒なら、長男が、この土地を相続した場合も、小規模宅地の特例が使用できる。
遺産分割では、相続税を減額するために小規模宅地の特例(措置法69の4)相続税の小規模宅地等の特例は自宅に対する特例ととらえられがちですが、アパートや駐車場など賃貸している土地を相続する場合にも適用することができます。
賃貸している土地は「貸付事業用宅地等」として、小規模宅地等の特例の対象になります。特例を適用すると、200㎡までの部分の評価額を50%減額できます。
家族問題は、森法律事務所にご相談ください。(TEL:03-3553-5916)
夫婦親子問題 https://www.mori-law-office.com/katei/
遺産相続問題 https://www.mori-law-souzoku.com/