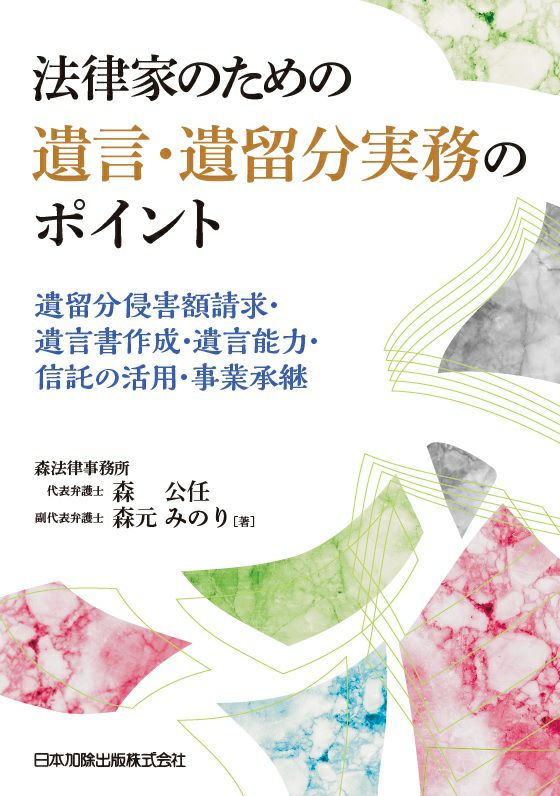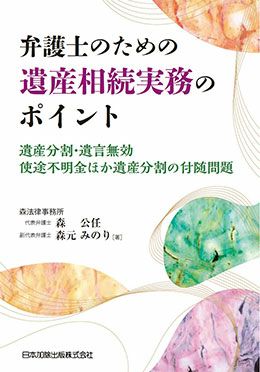森法律事務所から一言
遺言は、法定遺言事項違反、詐欺・錯誤、方式不備、公序良俗違反、遺言能力欠如で無効となります。
特に遺言能力は、法律法語であり医学用語ではありません。そのため、医師と裁判所の見解が異なることも珍しくありません。
また、遺言能力の意味を誤解しておられる方も少なくありません。例えば、遺言能力は15歳以上の意思能力、遺言能力の有無は医療記録のみで精査する、遺言能力は医学用語等々。しかし、このような考え方はいずれも誤解です。
弊所は、従来より、多数の遺言無効紛争事件を受任し、ノウハウを蓄積しています。また、そのノウハウを下記書籍で弁護士の先生方向けに公開し、多くの先生方が、この書籍を参考としておられます。特に「法律家のための遺言・遺留分実務のポイント」では、無効となった40の判例を分析し、裁判所の判断プロセスを解説している点は、他の著作では見られない特徴です。
書籍
法律家のための遺言・遺留分実務のポイント 遺留分侵害額請求・遺言書作成・遺言能力・信託の活用・事業継承
弁護士のための遺産相続実務のポイント 遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題
DVD
書籍より一層理解していただくために、下記動画を弁護士ドットコムさんから配信しています。